秘密保持契約書(NDA)は、知り得た秘密を保持することを取り決めるための契約書です。この記事では、その内容や必要性についてご紹介します。無料の雛形が利用できるサービスについても解説するので、ぜひ役立ててください。
秘密保持契約書(NDA)は、会社間での取引だけでなく、フリーランスで働く際にも必要になることがあります。
この記事では、その内容や必要性についてご紹介します。
無料の雛形が利用できるサービスについても解説するので、ぜひ役立ててください。
秘密保持契約書(NDA)は、知り得た秘密を保持することを取り決めるための契約書です。
英語で「Non-Disclosure Agreement」と表記されることから、その頭文字を取り「NDA」の略称で呼ばれることもあります。
秘密保持契約書の役割は、今後の業務で取り扱う情報の安全を確保することです。
社内の秘密情報を扱う人に対しての取り決めで、第三者への開示や漏洩をしない、業務を遂行する目的以外の用途で情報を利用しない、などの内容が含まれます。
個人情報やノウハウ、社内のみで扱っている情報など、秘密保持契約書を締結することにより守られる情報は多くあります。
秘密保持契約と似た言葉に、「機密保持契約」があります。
秘密保持契約と機密保持契約は同じ意味で使われていて、ほとんどの場合、違いはありません。
業務委託契約書は、業務を委託する人と受託する人が締結する契約書です。
秘密保持契約書とともに締結が求められる場面も少なくありませんが、両者には明確な違いがあります。
秘密保持契約書には情報を漏らさないための取り決めが記載されていますが、業務委託契約書には主に取引の概要が記載されます。
業務内容や報酬の取り決め、業務の履行方法、支払いサイクルや契約期間などについて記載されていて、これを締結することにより業務を委託するうえでのトラブルを未然に防ぐことが目的です。
関連リンク
業務委託契約書とは?必要となる状況および作成方法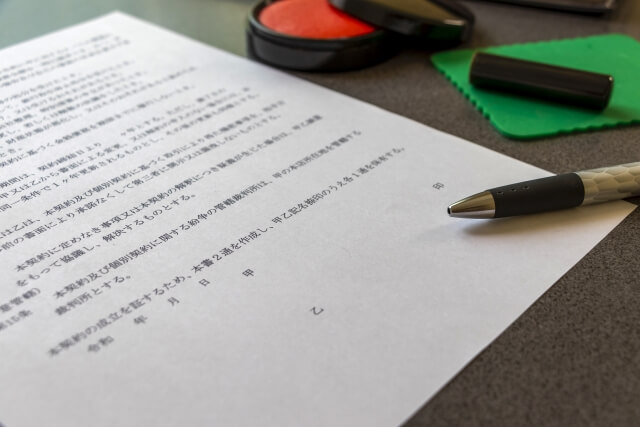
秘密保持契約の必要性については、以下のような場面にも表れてきます。それぞれ詳しく解説します。
特許法では、「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」である発明について、特許を取得できないことになっています。
このことから、今後特許を申請する予定があるのならば、秘密保持契約を締結して秘密を守っておくことが考えられます。
社外秘情報が漏洩し、他者がその情報を使って商品やサービスを作成するケースも想定できます。
この場合、この社外秘情報が不正競争防止法における「営業秘密」に該当するかどうかが大きな焦点です。
営業秘密に該当するかどうかは、その情報が「社外秘」として扱われていたかどうかによって変わります。
該当の情報に対して秘密保持契約を締結していれば、社外秘であると認められやすくなります。
この場合、秘密保持の範囲だけでなく開示許容者についての明記も忘れてはいけません。
情報が社外秘であり営業秘密に該当するのならば、万が一の際には商品やサービスの販売に対する差し止め請求や損害賠償請求が可能となります。
あらゆるトラブルを回避するための秘密保持契約ですが、どのタイミングで締結すべきかで迷うこともあるでしょう。
ここでは、締結のタイミングについてご紹介します。
営業活動における取引や商談では、企業のさまざまな情報を提供する場合があります。
特にBtoBでは、こうした営業活動を始める前のタイミングで秘密保持契約を締結しておくと安心です。
業務提携や資本提携においては、企業同士でさまざまな情報を開示することが多くなります。
これらの情報を漏洩させないためには、提携するタイミングでの秘密保持契約の締結が欠かせません。
秘密保持契約を締結するなら、不正競争防止法についても知っておく必要があります。
不正競争防止法は、不正な競争を防ぎ、企業間における公正な競争を実現するための法律です。
これは、前述した「不正競争防止」に関連します。
漏洩した社外秘が不正競争防止法の「営業秘密」に該当する場合には、差し止め請求や賠償請求などが可能となるのです。
不正競争防止法における営業秘密の要件は、下記の3つです。
秘密保持契約書は、他社と提携する際や社外の人に業務を委託する際などに、情報を開示することとなる際に締結されます。
提携や委託といった社外の人と連携して業務にあたるような場面では、さまざまな秘密情報を取り扱う場面が出てくるからです。
このように社外の人が秘密情報を取り扱う場合には、秘密保持契約書が必要といえます。
秘密保持契約書の締結により、自社の秘密を保持しトラブルを避けやすくなります。
秘密情報を多く取り扱うことになるM&Aが行われる場面でも、秘密保持契約書が締結されることが一般的です。
また、企業が従業員と雇用契約を結ぶ場面でも、秘密保持契約書を締結するケースが多いです。
秘密保持契約書だけでなく、情報管理規定や就業規則を設けることで、より情報の安全性を高めている企業もあります。
秘密保持契約書は、業務で扱う秘密情報の安全を保つために締結します。
締結する相手が、秘密情報の漏洩をしたり、情報を不正に扱ったりしないことを約束するための契約です。
これが契約書なしの約束であれば、万が一漏洩や不正があっても相手に責任を問うことは難しいでしょう。
秘密保持契約書を締結することにより、秘密情報が保持されなかった際の責任の所在を明らかにできます。
また不正競争防止法で定められた「営業秘密」を漏洩した場合には、損害賠償請求が可能です。
この契約があることで情報漏洩のリスクを抑えることができるうえ、秘密情報の対象を明確にすることで情報をより強固に守ることができます。
秘密保持契約書は、取引を始める前、情報を公開する前に締結するべきです。
契約書を締結する前に得た情報については、秘密保持契約書の効力が及ばないことがあるからです。
雇用契約を結ぶ場合は、入社手続きと一緒に済ませておくのがおすすめです。
秘密保持契約書に記載しておくべき内容には、下記のような項目が挙げられます。
契約書の効力を最大限に発揮するために、それぞれについて理解しておきましょう。
タイトルは、冒頭部分に記すのが一般的です。
「秘密保持契約書」のほか、両者ではなく相手に誓約をお願いしたい場合には「秘密保持に関する誓約書」などと題したものを相手方から差し入れてもらうのもいいでしょう。
契約書の場合は契約を締結する両者が署名捺印しますが、誓約書の場合は秘密保持の誓約をする側のみが署名捺印します。
前書きでは、契約の目的を記します。
今後の業務で知り得た情報を、どのような目的で使用するのかについて記載しましょう。
どの業務についての契約なのかを明確に記しておくことがポイントで、これが明確になっていないとトラブルになることもあります。
契約をする秘密情報とは、どの範囲の情報なのかをここで明確に定義しておく必要があります。
定義が曖昧だと、契約違反があっても責任を問えないことがあるためです。
「自社が開示する一切の情報」、「自社が開示する情報で開示の際に秘密であることを書面により明示した情報」等といった形で秘密情報の範囲を明確にしておきます。また、「秘密保持契約の内容、および、その存在」、「取引に関する協議や交渉の内容、および、その存在」を含めて、秘密情報として定義することもあります。
また秘密情報にあたらないものについても、ここで定義しておくケースが一般的です。
たとえば、「開示される前に受領側が既に保有していた情報」や「開示を受けた際には既に公知だった情報」などです。
開示側としては、知り得た情報はすべて秘密情報として扱ってほしいと考えるものですが、このように明確に秘密情報の範囲を定義しておくことで、受領側も秘密情報の範囲を明確に認識して保持しやすくなります。
秘密情報そのものを漏洩しなかったとしても、その複製などが出回ってしまっては意味がありません。
そこで、秘密情報の取り扱いについても厳格に定めておく必要があります。
「秘密情報を複製する際には、定められた目的の範囲内でのみ使用する」「複製したものは、原本と同じく保管および管理する義務がある」などと定めておくのが一般的です。
前書き部分で「契約の目的」を定めましたので、本項目では「目的外の使用禁止」を定めます。
「契約で定める目的以外に、秘密情報を使用することを禁止する」といった内容を記します。
秘密情報の返還・消去の項目は、後々のトラブルを避けるために有効です。
この項目があり適切に返還・消去の対応をしてもらえば、その後の漏洩のリスクは低くなりますし、万一、相手方が返還・消去の義務に反していたことにより、契約終了後のタイミングで秘密情報漏洩があった場合に、責任を問えることとなります。
「開示側による通知があった場合には、指示に従い情報の返還・消去を行う」などと定めておくのが一般的です。
万が一契約違反があった場合の損害賠償請求について定めるのが、この項目です。
情報漏洩などがあった場合にどのような範囲で損害賠償義務を負うのかについて、明記します。
また差し止めについても明記しておくことで、情報漏洩の抑止につながります。
本契約が、いつまで有効となるのかを定めます。
一般的には、業務取引や雇用と同期間に設定し、意思表示が特にない場合は自動更新していく内容が多いです。
また、契約終了後であっても、相手方に遵守させる必要がある場合には、「取引の契約が終了してから〇年間については、秘密保持契約は存続する」とするケースもあります。
案件を進めるうえで、契約外となる業務が発生することもあるでしょう。
そのようなケースに備え、「契約外となる事項や業務が発生した場合は、協議のうえで解決する」などと定めておきます。
また、「本契約について疑義が生じた場合も、協議のうえで解決する」などと記載しておくのが一般的です。
契約に関する訴訟が行われる場合に、審理できる裁判所をここに記載します。
万が一訴訟になった際にどこの裁判所で訴訟をするのかの取り決めとなりますが、これがないと自社に近い場所にある裁判所で訴訟を起こせなくなってしまうケースがあります。
契約を締結する両者の「万が一」に備え、必ず記載しておきましょう。
作成年月日は、調印の日とするケースがほとんどです。両者の同意があれば、作成年月日よりも前の日付から契約書を適用とすることも可能です。
遡る場合は「○○○○年○月○日に遡って適用する」といった文言を記載しましょう。
作成年月日から秘密保持契約書の効力が発生するので、情報開示のタイミングを図り年月日を決定しましょう。
また、両者の署名と押印をもって、契約が締結することになります。
まずは、ベースとなる秘密保持契約書のテンプレートを用意します。
企業それぞれにテンプレートがある場合には、どちらのテンプレートを使うのかについても、この段階で決めておきましょう。
秘密保持契約書は、取引基本契約書に盛り込む場合もあります。
ただし、より細かく秘密保持の内容を記載したいケースでは、取引基本契約書とは別で秘密保持契約書を作成するケースが多く見られます。
秘密保持契約書は、双方の合意がなければ成立しません。
どちらか一方のみが不利になることのないよう、双方で協議しながら内容を決めていくことが大切です。
懸念点がある場合には、リーガルチェックを依頼するのもおすすめです。
契約内容に双方が合意できたら、代表者がそれぞれ署名捺印します。
捺印は実印がベストですが、認印であるからといって無効にはなりません。
契約書が複数枚に渡る場合には契印を押し、改ざんリスクを抑えておくことも欠かせません。
秘密保持契約書を締結する当事者の数だけ契約書を作成し署名捺印したら、割印をしておきましょう。
関連リンク
割印とは?契約書への押し方とその大事な役割
第三者認証制度により個人情報保護体制を評価された事業者に付与される「プライバシーマーク」ですが、これを取得している企業で、万が一個人情報漏洩が起きてしまうと、プライバシーマークが取り消されてしまうことがあります。
このことから、従業員との間で秘密保持契約書を締結し、就業中は規則に則り適切に秘密情報を扱うとし、従業員が退職する際には、秘密情報の不正利用を防ぐための誓約書を書いてもらうと安心です。
契約書の中には収入印紙が必要なものもありますが、秘密保持契約書には基本的に必要ありません。
収入印紙が必要となるのは課税文書だけで、秘密保持契約書は対象外だからです。
ただし、秘密保持契約書の中に「請負」などといった課税文書対象となるものが含まれていると、収入印紙が必要になる可能性があります。
課税文書については下記の記事をご覧ください。
課税文書とは?印紙はなぜ必要?収入印紙代の一覧と貼付け不要になる方法を解説します
秘密保持契約書は、情報開示側と受領側がトラブルを避けるために、明確な内容で作成することが重要です。
記載漏れなどがあると、万が一の時に契約書の効力が発揮できないこともあるので注意しましょう。
電子契約システム「契約大臣」では、無料で使える秘密保持契約書の雛形をご用意しています。
雛形があれば契約書作成の時間を削減できるうえに、漏れが発生するリスクも少なくなるので、活用するのがおすすめです。
契約大臣は電子署名法や電子帳簿保存法に準拠しており、画面操作がわかりやすいのが特徴です。
リーズナブルな価格帯ながら、不明な点はメールや電話、チャットでしっかりサポートします。
操作についてのデモンストレーションも公開していますので、ぜひご検討ください。
かんたん・低価格・法律準拠の電子契約システム『契約大臣』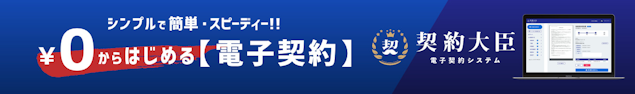
「電子契約ってどうやるの?」「導入したいけど、何を準備すればいいかわからない」
これから電子契約をはじめる企業や事業者の方におすすめの記事をご紹介します。
「電子契約のやり方を解説!電子契約システムの運営会社TeraDoxが自社例を公開」
※この記事は2022年4月時点の情報を基に執筆し、2023年7月に更新されています。

 電子契約システムの契約大臣サービスTOPへ
電子契約システムの契約大臣サービスTOPへ